インターネット上で生じる紛争類型と弁護士が代理できる業務
Contents
民事
インターネット上の名誉棄損等に対する法的措置
IPアドレスなど発信者情報開示
名誉棄損的言辞等を行った者を特定するための手続きです。
名誉棄損的言辞が行われたブログ、掲示板などのコンテンツプロバイダに情報開示を求めます。
IP情報や接続プロバイダに関する情報を開示してもらい、接続プロバイダに,名誉棄損的言辞等を行った者の氏名や住所などを開示してもらいます。
わたしの悪口が書き込まれてる!
しかし誰が書いたんじゃろうなあ・・・。
そうだよね。
まずはそれを確かめなくちゃいけないよね。
でもどうやって?
発信者情報開示という手続が用意されています。
発信者情報開示・・・
わたしが被害者なのに、そんな手間のかかる事をしないといけないのね・・・。
発信者情報開示は急がないといけない場合もあります。
特定費用は加害者に請求できるケースもありますが、全額とは限らないため慎重にご決断ください。
削除依頼
インターネット上に記載された名誉棄損的言辞などを,コンテンツプロバイダ等に削除してもらうよう、要請します。
発信者情報開示と併せて実施すると効率がいいみたいじゃな。
損害賠償請求
インターネット上に記載された名誉棄損的言辞が名誉を傷つけたことで発生した損害の賠償を請求していく手続です。
各種プロバイダに対するIP等の開示等は,損害賠償請求などの準備としての意味合いになります。
ばぶぶう(どこの誰かわかったら、こっちのもんだぞ!)
名誉回復措置を講じることの請求
民法723条に規定された名誉回復措置請求権の行使手続です。
基本的には,損害賠償請求に付帯して行われる場合が多いものです。
謝罪広告などが一般的ですが、とてもハードルが高い請求です。
電子商取引における消費者問題
インターネット通信販売等における消費者被害などの契約トラブルです。高額な商品を購入させられた,購入した商品の代金を振り込んだのに,品物が送られてこないなど,インターネット通信販売等における,契約トラブルについて紛争解決へ向けた交渉・訴訟などの可能性を検討するための法律相談を行います。
インターネットの消費者被害、増えています。
フィッシングサイトなど犯罪被害に関する損害賠償請求
インターネットを利用した犯罪も後を絶ちません。こうしたサイバー犯罪は犯人の特定も難しく,発生した損害を回復することは容易ではありません。そうした犯罪被害について,民事上で損害賠償を代理して請求していくことや、そうすることが適切か判断するための法律相談などをお受けすることができます。
気をつけないとネットには悪いヤツもいっぱいいるぞう〜。
著作権など知的財産権に関する侵害やライセンス関係のトラブル
インターネットは、ひとつのウェブサイトをとっても、プログラムや、文章、イラスト、写真、データベースなど、多くの著作物で構成されています。
また、企業のウェブサイト上では、商標権などの客体となっている画像データ、LOGOが存在しています。
ソフトウェアライセンス契約もインターネット上で結ばれるのが一般的とさえいえる状況です。
このような、インターネット上の知的財産権に関する様々な問題に関して,訴訟,交渉を行えます。
刑事
被害者側
サイバー犯罪の告訴等
サイバー犯罪の被害に遭われた場合,その,告訴などを行います。民事手続きよりも告訴受理のハードルが事実上高く,告訴手続には一定程度以上の資料(前提としてIPなどの開示など)が必要になるケースが殆どです。
加害者側
サイバー犯罪に関する刑事弁護
被疑者段階,被告人段階を通じて,サイバー犯罪の被害について,刑事弁護を行います。
被疑者段階においては,検察官との折衝をとおして,不起訴獲得を目指します。被疑者段階の刑事弁護が功を奏さず起訴されてしまった場合などは,刑事訴訟手続の中で弁護活動を担います。
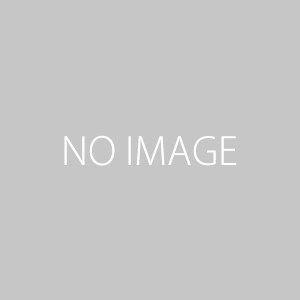
この記事へのコメントはありません。